医療ミステリと聞くと、「専門用語が難しそう」「理屈が多くて読みづらいのでは?」と身構えるかもしれません。
実際、『禁忌の子』には救急医療、不妊治療、出生の倫理といった専門領域が深く関わり、序盤は医療ドラマのようなリアリティの濃さに圧倒されます。また、会話が不自然に見える場面や時系列が把握しづらいなど、「新人作家らしい粗さ」も目立ちます。
しかし――それでも、ページを閉じられなくなる理由があります。
読者の心をわしづかみにする「最後の一撃」
本作最大の魅力は、物語後半で訪れる「鮮やかなどんでん返し」です。
第3章の最後の一行で「え!?」となり、終盤では声が出るほど驚かされる仕掛けが用意されているため、序盤で感じた読みづらさをひっくり返す破壊力があります。
ミステリとしての構造はやや荒削りです。
密室トリックは本格派には物足りないかもしれないですし、偶然が重なる展開には賛否がわかれると思います。しかし、それらを補って余りあるのが、フィナーレで明かされる真相の衝撃と、それによって初めて見えてくる「タイトルの意味」です。
読み終える頃には、「粗さすら、この結末のために必要だったのか」と思わされているはずです。
医療の難しさの奥に潜む、「子どもが欲しい」という切実な祈り
専門用語が登場するものの、本作は単なる医療知識の羅列ではありません。むしろ、「子どもを望む気持ち」が読者の胸に強く響く物語です。
自分の命を削ってでも子を求める親、閉ざされた環境で育ち、愛の形を知らないまま大人になってしまった子ども――。その願いと欠落が複雑に絡み合い、ミステリの枠を超えて読者の心を揺さぶります。
「医学用語の多さに苦戦したはずなのに、いつの間にか止まらなくなっていた」そんな体験ができます。
「感情」と「論理」――二人の医師が示す、生きるためのバランス
物語を支えるのは、救急医である主人公・武田と、冷静沈着な城崎という二人の対照的なキャラクターです。
- 感情の揺らぎに翻弄される武田
- 感情を切り捨て、論理だけで世界を捉える城崎
「人生には感情も論理も必要で、片方だけでは生きられない」というメッセージこそ、この作品の肝だと思います。
感情に任せすぎると人を傷つける。
論理だけに依存すれば、人を救えなくなる。
この二人の軌跡は、医療現場を描きながら、読者自身の「生き方」にまで問いを投げかけてきます。
心に残る読後感――救いと痛みの混ざった「イヤミス」体験
ラストには明るさの兆しが描かれるものの、「読後に妙な胸の痛み」が残ります。
それは、単にミステリが解決したというだけでなく、「人が人を想う気持ち」が複雑な形で結末を迎えるからです。
一気読みの爽快感と、じわじわ残る切なさ。この二つを同時に味わえる作品は、そう多くありません。
こんな人に読んでほしい
まとめ:粗削りで、だからこそ忘れられない物語
『禁忌の子』は、完璧なミステリではありません。しかし、だからこそ物語の熱さやキャラクターの真摯さが生きてきます。
読み進むほど、「何かを強く願う人間の姿」が心を掴み、最後には誰もが驚きの渦に巻き込まれます。
ページを閉じたあと、あなたもきっと、武田や城崎、そしてこの物語に込められた思いを忘れられなくなるでしょう。

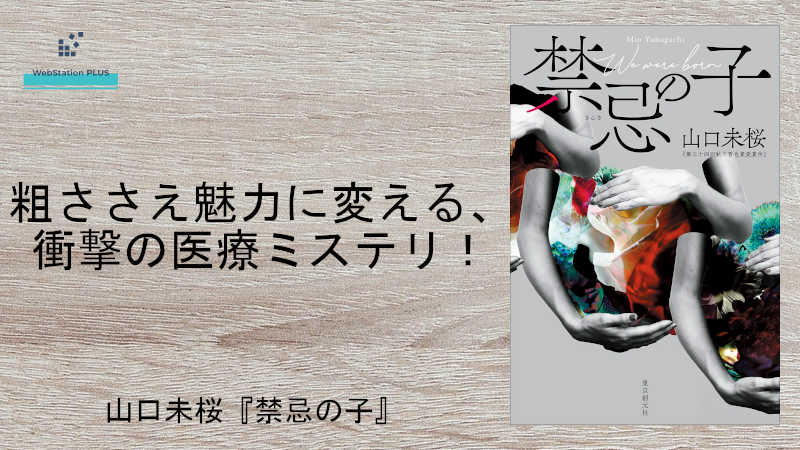
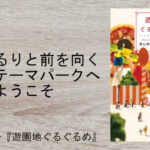
コメント